はじめに
久々に電気工事の積算をしている。積算と聞くだけで気が狂いそうな人も世の中には一定数いると思う。
自分もその一人である。新入社員の時にはやり方がまったくわからず発狂しかけた。
ゼネコン・サブコンにいてガチで積算している人には到底かなわないですが、やりかたのひとつを知っておくだけで、実際やる時には少し気持ちが楽になると思う。
これが正解、という訳ではありません。あくまでも自分が経験したり、人に教えてもらったこと。それらをまとめて誰かの役に立てればと思い記事にしてみました。
電験やエネ管を取得したあと、こういったタスクをすることが増えたという声も聞きますので。
関連記事↓
積算とは
積算とは、建設工事や製造業などで必要な費用や資材の数量を事前に見積もる作業のこと。
設計図や仕様書などをもとに、材料費、労務費、機械使用料、諸経費などを細かく計算し、総工事費を算出すること。
恐らく大きく分けて3つくらいに意味合いが分かれると思います。
①【概算積算(初期提案・事業化検討)】
いわゆるざっくり概算のやつ。エイ・ヤーで出しました、なんて時はこんな時。
- 1kWあたり〇円」「m²あたり〇円」など単位ベース
- 太陽光では「1kWあたり20〜24万円」(規模やオーダーによって結構変動ある)など
- 500kVAキュービクル設置工事一式で1,500万とか
ざっくり、何かの事業のライフサイクルコストの把握する時なんかに使われますね。
②【実行予算積算(施工者側)】
このやり方が必要になる人が一番多いのでは、、、と思います。単純にピラミッドの頂点よりその下の方が増えるからね。
この時、自分が良く使う考え方が、以下の通りです。
労務費、資材費、副資材費、その他(重機、試験費、試験書類作成費用 etc )で直接費を出し、それを元に関節費用を出す。
これについては、後ほど詳しく書いてみようと思う。
③ 【設計積算(発注者・設計事務所・官公庁)】
自分は官公庁では働いたことがないので、ちょっとよくわからん。が、「公共建築工事積算基準」などを元に積算や査定することが多いと思う。
自分が発注者側で積算していた時は、予算を申請する時は①の概算積算を使って、査定をする時は、上の「公共建築工事積算基準」だったり、「積算資料」「建設物価」を使って単価査定をしたりしてた。
ひとことだけ最初に言っておくと、一番良いのは在籍する会社での過去の実績から判断することです。あるいは、見積もりを複数社とって比較分析することです。それでも、積算しなきゃいけない場合の考え方のひとつということで。
②【実行予算積算(請負側)】
これは多分正式名称じゃないけど、結構、この呼び方で使っている人は多い印象がある。
お客さんの要望通りの金額で本当におさまるのか、どれくらいの利益が出るのか、そのためにどの項目をどの程度におあめなきゃいけないのか、を考える時に必要だったりする。
自分はは、最初の会社で教えてもらった以下の方法を採用しています。
工事費の体系
以下のようになってます。
体系
└ 工事費
├ 工事原価
│ ├ 直接工事費(労務費・材料費/機器費 ・その他)
│ └ 間接工事費
│ ├ 共通仮設費(仮囲い・現場事務所・仮設トイレなど)
│ └ 現場管理費(現場監督の人件費・通信費・安全管理費など)
└ 一般管理費(本社経費など、現場以外の管理費用)
工事費 = 工事原価(直接+間接)+ 一般管理費
例)
直接工事費 75%
共通仮設費 5%
現場管理費 7%
一般管理費 8%
——————–
合計 100%
1.労務費
労務単価×工数=労務費でござる。
労務単価は、1日の労働時間を8時間として、その人に1日働いてもらった時の単価。
工数は、作業を終わらせるために必要な日数。
例)電工の労務単価が25,000円/日 → 電工1人が4日働くと10,000円の労務費。
そこでひとつポイントなのが、単価25,000円/日と4日という価格が本当に正しいのかということ。
< 労務単価を調べる方法>
・公共工事設計労務単価(国土交通省)
職種ごとの地域別単価。
・都道府県発行の単価表
地方自治体が独自に発行している場合あり。
<工数を調べる方法>
歩掛(ぶがかり)を使う
・「歩掛」は、単位作業あたりに必要な作業量の目安
「土木工事積算基準」「電気設備工事積算基準」などに記載。
たとえばだけど、
VVFケーブル布設工事(露出配線)、2.0mm×3心、片側支持、金属製サドル使用で、
0.0045人日/mという情報を見つけたとする。
1000mの敷設工事をしたい、ってなったら、
0.0045人工/m × 1000m = 4.5人工
25,000円/人工 × 4.5人工 = 112,500円
※人工(にんく)は「人×日」の意味で、人日(にんにち)と同じように使われます
となります。
2.材料費/機器費
機器費は、メーカーとかだったらメインとなる機器ですね。太陽光だったら、パネルとか架台とか、蓄電池とか。これは価格がオープンになってることが多いと思うので、あまり迷わないはず。
材料費は、上の機器以外の電気工事で使う材料のこと。
資材費と副資材費に分けます。
材料費:VVFケーブル(2.0mm×3C):120円/m × 1000m = 120,000円
副資材費:金属製サドル 15円/個 200個 3,000円、ビス・プラグ等小物類 ― 一式 2,000円
などです。(イメージ)
んじゃこれをどうやって調べるのって話です。
<材料費を確認する例>
・積算資料などの(書籍・データベース)で確認
・ショッピングサイトの0.8掛けくらいと想定
・仕入単価と売上価格の中間値
(例:メーカー希望40,000円 → 市場価格28,000円 → 積算値32,000円で登録)
・副資材費:配線固定具・コネクタ・端子等(資材費の5〜10%)→かけ率で算出するのは本当にケースバイケース、、、
こんな感じで算出します
3.その他(重機、試験費、試験書類作成費用 etc )
これもまちまちですが、、。
重機
1. 歩掛ベースで積み上げ
例:高所作業車(10m未満)を1日あたり○○円×必要日数 建設物価(施工編)や「公共工事積算基準」に載っています
ただ、正直これもめちゃくちゃ経験がないと想定できないです。自分もこのあたりは正直、詳しいと胸を張って言えないので、土木の人に相談したりしてます。
2.掛け率で想定
電気工事全体費に対して 1〜3%(大規模搬入ありなら5%程度まで)
労務費に対して 5〜10%(高所作業・掘削補助などがあれば)
例)労務費が300万円 → 重機費 15〜30万円程度
ここは個人的に難所なので、詳しい人に相談しても分からなければ賭け率、そして多めに一式で入れたりしてます。
運搬・搬入出費
資材費または機器費の5〜8%
正直これも困った時頼みの方法です、、。
その他 よく分からない謎の項目
ここまでで、経験した工事や、推定した項目はすべて積み上げたと仮定します。
それでも、謎のコストは入ってきます。大規模になるほど入ってきます。その時のために、実行予備費など、適当な項目で予備となる費用を確保しておきましょう、、。
なので、労務費、材料費以外はかなり経験と想像力が必要となると思います、、。
メーカー系の工事や試験には注意
これも大事です。
メーカー系、いわゆる重電さんとか精密機器メーカーさんとかは、過去実績から想定しないとほぼ無理です。
めちゃくちゃ高いです。(給料も高いからだと思います、、もちろん技術も確かなんですが)
労務単価でいうと、¥80,000/人工とか100,000/人工とかざらです。また圧力計みたいな市場価格でせいぜい15万くらい?のものが100万近くで見積もりされることもあります。
絶対に値下げしません。これは絶対です。
間接費
現場の施工に直接関わらないけれど、工事を進めるために必要な費用のこと。これは「直接工事費」に対しての補助的・管理的な費用でござる
だから、これは直接費が決まった後に、鉛筆なめながら調整します。
多くてもだいたい20%程度におさまることが多いような気がします。
土木工事と電気工事を直接費としてまとめて、それに対して掛け率で算出しているところが比較的多い気がします。
まとめ
自分が、半導体メーカー発注者と太陽光発電システムEPCとして働いていた時はこんな感じでした。
ただ、正直、体系的に教育を受けた訳でもないので、他にやり方はたくさんある気がします、、。
それでも何かの役にたてれば嬉しいです。
| 書籍名 | 内容概要 | 発行元・出版社 |
|---|---|---|
| 建設物価(施工編・資材編) | 材料単価、重機費、労務費などの市場価格が掲載された積算の基礎資料。公共工事・民間工事問わず使用される。 | 一般財団法人 建設物価調査会 |
| 積算資料(建築・設備編) | 建築・電気・管工事など、各種工種ごとの材料費・歩掛が掲載。実務者の必携書。 | 一般財団法人 経済調査会 |
| 公共建築工事積算基準 | 官公庁発注工事における積算基準書。設計積算や積算根拠の裏付けに。 | 国土交通省 官庁営繕部 |
| 電気設備工事積算実務マニュアル | 電気設備工事に特化した積算解説書。施工者向けの実務マニュアルとしても優秀。 | オーム社 ほか |
🌐 サイト・オンラインデータベース一覧
| サイト名 | 特徴 | URL |
|---|---|---|
| 建設物価調査会 | 「建設物価」「労務単価」など、各種価格資料を発行。電子版もあり。 | https://www.kensetu-bukka.or.jp |
| 経済調査会(積算資料Web) | 積算資料の一部データをオンラインで閲覧可能。歩掛や資材価格を調べるのに便利。 | https://www.keichosa.or.jp |
| 国土交通省|公共工事設計労務単価 | 毎年更新される職種別の労務単価一覧。PDFで全国分が見られる。 | https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000298.html |




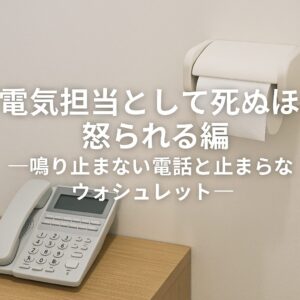

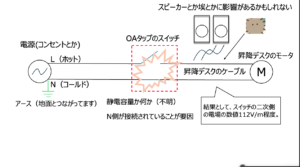


コメント